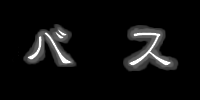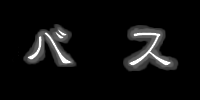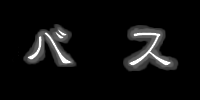
3
「…………おか〜さん、暇だよぅ」
そんな時、そう言い出したのは、先ほどの女性に連れられた少女だった。言葉通り、思いっきり不満を顔に出して所在無さげに足をぷらぷらさせている。
「もう少しの辛抱よ。ちょっとの間だから、我慢してね」
眉尻を下げ、困った風に諭す女性。少女もあまり自己主張する方ではないのか、顔の不満をそのままに黙ったまま足をぷらぷらさせ続けている。
母親の方もそれには申し訳なく思っているらしく、飴玉をバックから数個取り出して少女の方に、「どれ食べる?」と勧めている。
「…………ん、こっち…………」
少々無愛想に迷っていたが、美味しい飴の誘惑は耐えがたかったらしい。差し出された飴を受け取り、包み紙を取って口に放る。
無表情だった顔が、しばらく舐めている内、自然と綻んでいく少女。それを横からほっとした表情で眺めている母親。見ていて微笑ましくなる光景だ。
「――あなたも、いかがかしら」
その母親がそんな事を、こちらに振り向きながらが言った。
「…………いえ…………」
少々油断しすぎていたようだ。何とはなしに二人を眺めていた自分。こちらに話題を振られるのは予想してしかるべきだった。
そんな風にちょっと狼狽していると、少女までもがこちらに注目しだした。
……そんな興味心身な目でこちらを見るのはやめてほしい。
「…………いる?」
娘さんにまで勧められてしまった。……まあ、そんな無垢な瞳で勧められては断れない。
「……いただきます」
と、母親の差し出していた飴玉を受け取った。にっこりと笑う母親と少女。なんか知らないが、負けた気分。
先ほどまであった殺伐とした雰囲気が嘘のようだった。訳の分からない満員の乗客によるプレッシャー。謎の爺さんによる謎の言葉。急に豹変した青年のギャップ。不可解な出来事の連続に緊張していた神経も、ここに来てすっかり弛緩した様だった。
しばらく飴をなめ続けて大人しくしていた少女だったが、元来落ち着けない性格なのだろう。急にきょろきょろしだした。
「……ん〜?これなーに?」
と、人見知りする風でもなく、好奇心を示した少女の対象は、鞄からぶら下がった一つのストラップだった。緑色をしたアザラシのような物体。
「ん?ペットボトルに付いていたおまけだ」
「ほ〜、ふ〜ん」
などと呟き、窓側の席から懸命に体を伸ばしてストラップを触ってくる。言葉少なだが、異様に関心を示している。
「あ、こら。す、すいません」
母親が慌てて少女を嗜める。
「いえ、いいですよ。……なんだったら、あげようか?」
「え?いいの?…………でも…………」
と、教育が行き届いているのか矜持の問題か、難色を示す少女。だがその手がストラップを離さない事から、すっかりこのアザラシが気に入ってしまった様子だ。
「いいよいいよ。どうせおまけで貰った物だし。似たようなものは他にもある」
「本当に、いいんですか?」
と聞いてきたのは母親の方。少女の方はすっかり貰う気で、目を輝かせている。
「いいですよいいですよ。飴のお礼だと思ってください」
と言いながらストラップを外し、少女に手渡す。
少女は喜色満面の笑みでそれを受け取り、席に戻ってそれを掲げている。
「……どうも、すみません。ほら、千尋。このお兄さんにお礼を言いなさい」
千尋と呼ばれた少女は笑みのままこちらに振り向き、「ありがとうございます」、と礼儀正しくお礼を言った。
「良かったわね、千尋」
「うん」
と返事をする少女は、ストラップにもう夢中になっている。
母親の方は自分の娘の頭を撫で、ふと、表情に翳りを見せた。
「?」
何故?と心中で疑問符を作る俺に対し、その母親は改めてこちらに向き直った。
「本当に、重ね重ね礼を言いますが、ありがとうございます」
「い、いえ。そんな大した事はしていませんから」
そんな風に改めて礼を言われれば、こちらが恐縮してしまう。ただでさえ自分は、他者から礼を言われるのに慣れていないのに。
そのとき、すっと、女性の顔つきが真面目なものになった。
「……もし、よろしければ………………」
「……え?」
女性の口が開いたまま止まった。時間にして数秒。
閉じたと同時、ゆっくりと娘のほうへ首を向ける。
少女の方は、怪訝に母の方を見ていた。首を傾げ、キョトンとした顔で見つめ返している。
ふっと母親の顔が柔らかくなり、こちらに顔を向けなおした。
「……いえ、何でもありません。……宮の里へ行くのでしたね?」
「え、えぇ」
「あそこはバス停が崖の近くでもあります。どうぞ、お気をつけて下さいね」
「……はい」
――結局、彼女が最後、何を言おうとしていたのか、聞きそびれてしまった。
バスは次第に、急な勾配の多い山間へと差し掛かる。少々揺れバランスも悪く、曲がりくねった道も多い。車酔いしないか心配だ。
そんな中、……実にバランス良く、のしのしと歩いてくる人が一人。
先ほどの青年を介抱していた男性だ。体格にマッチした優れたバランス感覚で、こちらへと近づいてくる。
「眠ったようだ。放心状態も脱したようだし、もう大丈夫だろう」
彼はそう逞しい声で宣言した。なんというか、明らかに体育会系だなあ。
「君は、彼の知り合いかい?」
そう聞いてきたので素直に応える。
「いえ、今日このバス内で初めて出会ったばかりです」
「ほう?そうかそうか。一期一会、縁というものは大事だ。出会った中で友が出来るというのは良いことだし、その縁を大切にする事もまた然り。……と、私が言えた事ではないし、言うような状況でもないな…………」
照れくさそう、というより、なんだか申し訳なさそうに頭を掻く男性。俺は軽く、「はあ」、とだけ返事をした。
「君は宮の里へ行くんだったね?どうしてあんな寒村へ?」
と、先ほどの老人と同じ事を聞かれた。男性の表情は既に変わり、今は友好的な笑みを浮かべている。
「ええ、大学のゼミで、住んでいる人達へインタビューをしに行くんです」
「ほう。学科は?」
「文系、人間科学科です」
「ふむふむ、よう分からんが、なんか難しそうだなぁ」
ひょうきんな顔をして頷き続ける男性。なんとなくユーモラスな人だ。
「俺は、大学は体育科の出だったからな。勉強なんかさっぱりだった」
印象どおりの人だ。見れば分かる、と言っても過言ではない。
礼儀として、こちらも質問し返した方がいいだろう。
「……、そちらは、どうしてこのバスに?」
「うん?」
青年の件があるから明確な答えは期待していなかった。ただこの人なら、何らかの形で応えてくれると思った。先ほどの青年のようにパニくる事もなさそうだし。
予想通り、少しの間言葉を選んだ素振りを見せ、明確な一言を答えた。
「そうさなあ。一言で言うと、償いに、だ」
「償い?」
「おっと、ここから先は言えんよ。まあ何だ。後で分かるようなことだ。その時になるまでお楽しみ、って事でな」
男性は明朗快活に笑った。
「?はあ……」
後で分かる?この先の寒村と、何か関わり合いがあるのだろうか?
だがこの質問を繰り返しても、彼は何も答えそうには無かった。それに、もう目的地は目と鼻の先だ。
『次。宮の里、宮の里です』
繰り返されるアナウンス。正面を見てみれば、坂を上り切った所にぽつんと置かれたバス停の標識。
着いたのだ。ようやく、ゼミの課題地へ。
これから課題を行うのだ。バスなど交通手段でしかないが、彼はまるでバスに乗ることこそが主目的の様に感じ、早くも疲弊していた。
バス内のボタンを押し、降車を知らせる。
「おっと、目的地に着いたのか。ここでお別れだな。暇つぶしに付き合ってくれて、ありがとう」
「あ、いえ。そんなことは」
返事に、にっこりと男性が笑う。
そして、バスが止まった。
手を振ってくる先ほどの女性と娘、男性に手を振り返し降車口まで向かう。
途中、最初に会った老人の席を過ぎ去った。彼はじっとこちらを見つめ、ゆっくりと会釈をした。
…………今のは、別れの挨拶だろうか?
運転席へとたどり着き、料金口に整理券とお金を投入する。
これで、お終い。
不気味だった、このバスともお別れだ。
タラップを降り、久しぶりの地面に降りる。
軽く周囲を見渡すが、駅前と同じで日差しが強くセミがうるさい。開けた場所で、道路の行き先に林は無く、青々と茂った山々が連なっているのが見える。この先がカーブになっているのだろう。
その見渡すついでに、今まで乗っていたバスへと振り返った。
まだドアは開いており、その先に運転手が見える。
彼はそっと、帽子を脱いでお辞儀をした。
は?と疑問に思うと同時、ドアが閉まって再びバスは発車した。
……何の深い意味も無い。ただでさえ不可解なバスだった。最後の最後まで不可解なのは当たり前だ。
――ただ、予感はある。このままで終わるはずが無いだろう、と。ここまで自分を翻弄し続けたバスだ。
不可解は、続いている。
じっとバスを見送る視線の先、後部座席に、先ほどの青年の姿が見えた。眠りから覚めたみたいだ。
彼は弱々しく手を振って、自分へさよならの挨拶を送っている。
最初に出会ったときのハイテンションが嘘のように。
バスはどんどん加速して、彼の姿もやがて小さくなっていき、
ふと、なくなった。
青年の姿が?
そう。
何で?
当たり前だろう。
バスが崖の奥へ消えたんだから、彼の姿も消えるに決まっている。
急いで駆けた。バスが落ちていった崖へと。
駆けていく途中で響く破壊音。もはや自分が駆ける意味は無いけど、だけど、そうしなくてはいけない気がした。
やがてたどり着く。そこはガードレールだけで守られた、急カーブの絶壁近く。
壁面には木々などなく、生えているのは僅かばかりの草ばかり。落ちていったバスを途中で受け止めるだけの力など無く、バスは、重力に従い、落ちていった。
下には惨劇が広がっている。
ひしゃげた車体。
原形を留めぬ、壊れたスクラップ。
その正体を知らぬ方がいい、赤い染み。
それを前にして、ただ自分は意味もなく、――映画みたいに、爆発しないんだな――などと、考えていた。
<< >>