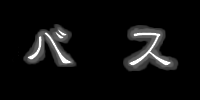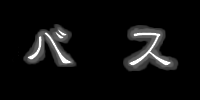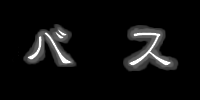
1
事の始まりは至って平凡。ゼミの実地研修の直前、使ってた軽のミラがエンストを起こしてしまった事が発端だと思う。
結果、見事にエンコだった。見た感じヒビがはいっていてどうにもならない。元々叔父から譲り受けたものなので愛着はそれほど無いが、これほどのオンボロに気づかず乗っていたとは恐ろしい。叔父さん、あんたどんな車の使い方してたんだ?
まあそんな訳で、もういっその事、新しい車を買い替えることに決めた。ミラに乗っていた半年間の間に貯金も十分貯まったし、そろそろ染みのついたシートも眺め飽きた頃合だ。今度どんな車を買うかはさておき。
直面する問題は車を買うまでの足代わりのことだ。
何故か文化人類学の教授が主催するゼミを取ってしまったばっかりに、休日返上で山奥に行かねばならない事態に陥った。簡単な話だ、その教授がフィールドワーク専門だったというだけの事。その反面、課題は面倒極まりない。
昔ながらの製法で工芸品を作って生計を立ててる爺婆にインタビューして、その地に根付く慣習を読み取り、それを他地方の文化や他国の文化と比較し、独自の体系付けを書面上に確立し、それらをまとめたレポートを提出せよ、との、全くクソ面倒くさい課題を出されたのだ。色々と教授に申したてたい事はあったが、友の千治が意外に楽しそうだったので諦めた。どちらにせよあの偏屈が決めた決定は覆らないだろう。車が故障中だというのに、まったく間の悪い。
そういう事で、俺は次の休日、隣県の村まで行かねばならない。
友人は全員自家用車で行くらしい。俺も乗せていってくれと頼んだが、断られた。免許を持っていない奴も相当数いるらしく、定員オーバーに達したとの事。レンタカーという手も考えたが、やはり電車やバスのほうが安上がりだと思い止まる。
まあそんなわけで、目的の寒村まではバスで行くことにした。
目当てのバス停は、寂れた駅前にひっそりと立つ看板によって見つけることが出来た。
まあよくもこんな辺境まで来たものだと思う。見渡しても見渡しても娯楽になるものが何も無い。せいぜいあの寂れた建物のパチンコ店ぐらいか。
他にでかい建物は廃ビルばかり。それも二、三棟しか立っていない。他は更地になっていた。開発計画があるわけではなく、単に疎化が進んでいるだけだろう。
もちろんバス停は標識一本の、何ともアレな暑い場所だ。今の自分に出来ることは、出来るだけ木立の影で佇んでいる事ぐらい。
待っている間、非常に手持ち無沙汰だった。節約が身に染み付いているためオーディオプレイヤーも持っていない。耳に聞こえるのはセミの大合唱だけ。もうそろそろ夏本番。長い長い夏休みももう目前だった。
暇さもそろそろ我慢の頂点に達していたので、千治に電話を掛けてみる。二年も使ってボロボロの携帯を取り出し、慣れた手つきで戦時の電話番号を呼び出す。
数回のコールの後、電話に出る千治。第一声はとっても呑気さが滲み出ていた。
『やっ、笙。どうしたんだい?』
「暇だ。とても暇だ。退屈なぐらい、暇だ」
『そうかそうか、暇か。って、そう言われても、こっちにはどうしようもないねぇ。もう僕たちは着いちゃってるよ?』
「そうかいそうかい。こっちは未だバスも到着していない。一日に三本発着って何の冗談だ。というか、もう到着時刻は過ぎてるように見えるんだがこれどうよ?」
『本当に?ちょっとそれはおかしいねえ。というより、異常?』
と、千治の声には疑問符が滲み出ていた。
「異常?異常ってほどでもないだろ。俺がバス通学してたときも、普通に良く遅れてたぞ?」
『高校の時の話かい?そりゃあ君の住んでた町は都会寄りだったから、バスが普通に遅れる事もあるだろうさ。だけどここは田舎も田舎、大田舎。人が大勢乗ることも無いはずだし、渋滞になるほど交通網が悪いわけでもない』
ふむ、そう言われてみるとそうだ。確かに遅れている現状はおかしい。
『それにね。小耳に挟んだんだけど、そこのバスって一週間に一人の乗車率らしいんで、廃線も検討されているほどの寂れ具合らしいよ。うーん、もしかしたらやる気をなくした運転手さんがスト起こして本日運休かもしれないね』
「嫌な事言うなよ。もしゼミに間に合わなかったら、俺あの頑固爺にどんな宿題出されるか分からんぞ?」
『あはは、まあそうなったら……ご愁傷様?』
「こっちにまで迎えにきてくれる優しい配慮は無いのか?」
『そしたらこっちが遅れちゃうよ?まあ、車が壊れちゃったのが運の尽きだね』
まったく冷たい言葉だ。友達甲斐が無い。
いや、ほんとに遅れたらどうしようか。やだぞ?一人黙々と教授が集めた資料の編纂を物置でするのなんて。
と、そろそろ罰の不安が明確になり始めた頃、まだかまだかと眺め続けていた曲がり角から、ようやくバスが現れた。
「ああ、ようやくバスが来たみたいだ。居残りさせられずにすみそうだな」
『良かった良かった。居残り手伝ってって泣き付かれても面倒だしね』
……冗談による発言だよな?いくらなんでも、素でそんな発言をする人間を友人に持った覚えは無い。
「……じゃ、現地で」
『いー。ばあ〜い〜』
のやり取りを経て、通話が切れた。と同時にバスが停車する。
停まったバスは白の基本色に赤のライン。以前良く利用していたのと同じ型だった。
ドアの縁にある錆、曇りきったドアのガラス、ステッカーや塗装は所々剥げている。相当年季が入っているらしい。日光を背景にしていて薄暗いため、実態よりさらにボロく見える。
ひび割れた音声と共にドアが開いた。向かいの窓から差し込む日光がわずかに視界をくらませる。
少々高い足場に乗って、手元近くに出された整理券を取る。そして一歩踏み出し、
気がついた。
バスの乗客全員に、じぃっと、見つめられていることに。
……誰を?
……俺を?
そう、周りのみんなが――――。
バスの中には、たくさんの乗客がいた。それらの誰もが、例外なく俺を見つめている。
髪を染めた若者、中年の女性、初老に差し掛かっただろう夫婦らしき二人、制服を着た中学生、そして運転手。誰も彼もが感情の浮かんでいない顔をこっちに向けている。
セミの音が、――遠く聞こえた。
――自分は、何か、異世界に踏み込んでしまったのだろうか?どこかで、何かを間違えたのだろうか?――
こちらを見つめる目、目、目。背筋が凍る、足が竦む。何も悪いことはしていない筈なのに、許しを請いたくなる光景。
「…………あ、いや…………あの…………」
思わず何か言わなければと思って出た言葉が、これだった。どもって、哀れなほど萎縮し、まるで意味を成していない呼びかけ。
ぼそりと、一番近くに座っていた老人が何か言葉を発した。
「…………どこまで?……」
「えっ!?」
ほんとに唐突だった。不覚にも悲鳴に近い叫声をあげてしまった。
「…………どこで、降りるんだい?」
ほとんど失礼な態度に怒った様子もなく、ただ淡々と聞き返す老人。目深にかぶった帽子に隠れた目は、こっちを見ているように思えない。ただただ真正面を向いているようだった。
「え、あ…………宮の里、です……」
それを聞くと見つめてきたほとんどの人々は、関心を失ったかのように目を戻した。ある者は窓の外、ある者は自分の手元、ある者は目を瞑って空を仰ぐ。老人は顎を上げ、目線を運転手のほうに向けた。
なぜかバスの運転手が確認するように頷き、ドアが閉まる。途端に昔見慣れていた光景へと車内が変わったように感じた。違和感が若干薄まる。
バスが、発車した。
……自分は何か、とんでもない世界に迷い込んでしまったのではないだろうか?
バスは聞いていた話と、まったく違う様子を見せている。閑古鳥が鳴くどころか、座るところさえない。
乗客は全員通夜のように押し黙り、車内には響くエンジン音以外の音が無い。
――黄泉路へ向かうバスの話を知っているだろうか?――
もしかして自分は、あの世行きのバスへ乗ってしまったのではなかろうか。
笑えない冗談だ。状況が状況だけに一層そう思う。
この窮屈で息が詰まりそうなバスを三十分近く、ずっと立ちっぱなしで我慢しなければならないのだろうか?そう思って思わずため息が出そうになった時。
ぽんっと、肩を叩かれた。
それだけで背筋は凍りつき、息が一瞬詰まる。
引きつる頬のままに後ろを振り返ると、手の主は先ほどの老人だった。帽子に隠れていた顔が今は晒されていて、相当年季が入った表情が目に映る。
「……君は、何用で――宮の里へ……?」
「えっ、…………だ、大学の、――ゼミで、」
ほう、そうかそうか、と老人は相貌を崩す。深い皺の刻まれた顔が笑顔でさらにしわくちゃになる。
「うん、大学はほんに人生のためになる学問を教えてくれる。くれぐれも勉強を疎かにしてはならんぞ……」
「は、はあ……」
老人は幾度かうんうんと頷くと、ぶつぶつと独り言をつぶやき続けた後押し黙ってしまった。もはやこちらに関心を向ける様子は無いようだ。
…………訳が分からない。いったいこの老人は何が言いたいんだ?
また、車内を沈黙が支配する。会話があった後なので、一層気まずい。
<< >>